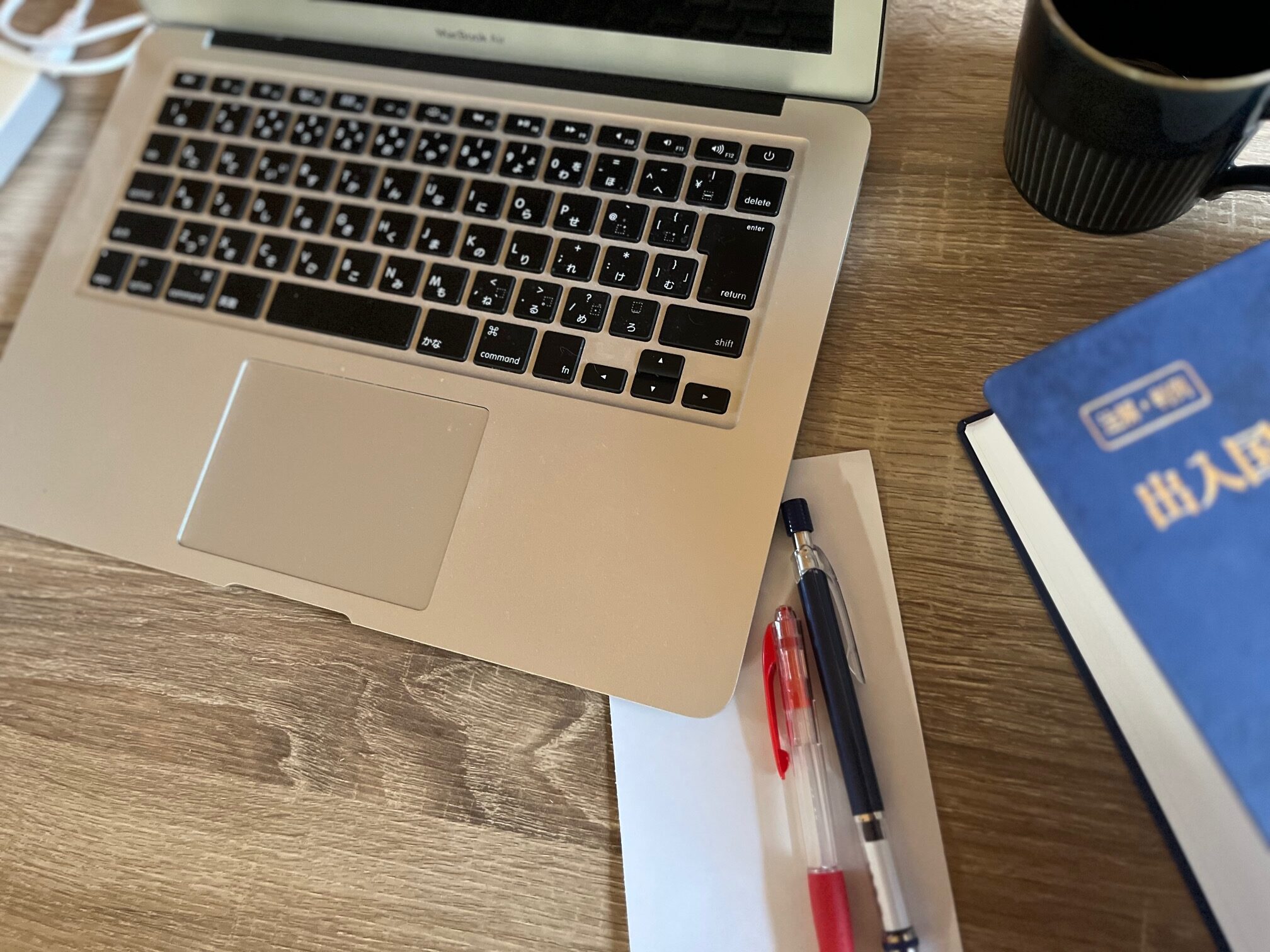ー会社を設立したいー
設立手続き
設立手続きの中心人物は発起人といいます。発起人の資格は特に制限はありません。未成年でも法人でも発起人になれます。また、人数制限もありません。未成年者が起業して会社を設立しても何ら問題はないのです。
設立方法は発起設立と募集設立の2種類あります。発起設立は、設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受けて設立する。募集設立は、設立に際して発行する株式の一部(最低1株)を発起人が引き受けますが、残余については他から引受人を募集して設立します。こちらは創立総会を開催することが必要です。
会社設立はまず定款作成からスタートします。これは株式会社の組織・活動を定める根本規則のこととで、いわば会社の憲法のようなものです。作成した定款は公証人の認証を受けることで効力を生じます。
定款記載事項
絶対的記載事項
- ①目的
- ②商号
- ③本店の所在地
- ④設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
- ⑤発起人の氏名又は名称および住所
- ⑥発行可能株式総数
ここで注意したいのは公開会社の場合です。設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の1/4を下回ることはできないというルールがあることです。そして定款は、会社設立後株主総会の特別決議により変更することが可能です。
変態設立事項
会社法28条に記載された4つの事項のことです。(すべて調査役の調査が必要)
- 現物出資(金銭以外)
- 財産引受(発起人が特定の財産を譲り受ける)
- 発起人の報酬・特別利益(会社設立企画者の功労に報いる)
- 設立費用(定款に記載)
発起人の責任
会社設立時の発起人責任は重い。次の4点は念頭に置きたい。①定款に定めた額に著しく不足するときは発起人は会社に対してその不足額を支払う義務を負う。②会社に対して、金銭出資における払い込みを仮装した場合、仮装した出資に係る金銭の全額の支払いをする義務を負う。③任務懈怠によって会社に損害を与えた場合の賠償責任。④職務を行うにつき悪意または重過失によって第三者に損害を与えた場合の賠償責任。このように発起人の責任は重大です。
設立の手続きへ
発起設立の場合は、発起人が出資予定額すべてを払い込み、その後取締役などの最初の経営陣を選びます。募集設立の場合は、発起人が出資額を払い込んだら、他の出資者を募集し、応募した人は期日まで出資金を払い込みます。支払い完了後払い込んだ銀行から「払込金保管証明書」を発行してもらいます。発起設立では創立総会を開催して取締役を選任します。いずれにおいても設立手続きが済み次第登記をして会社が誕生します。
定款変更の場合
公証人役場で定款認証後会社設立登記済みの場合で、その後の定款変更は公証人役場での認証は不要。
1.株主総会での特別決議
2.議事録の作成
3.法務局へ登記
4.税務署へ(決算月変更など)
5.原始定款と一緒に定款変更議事録を保管