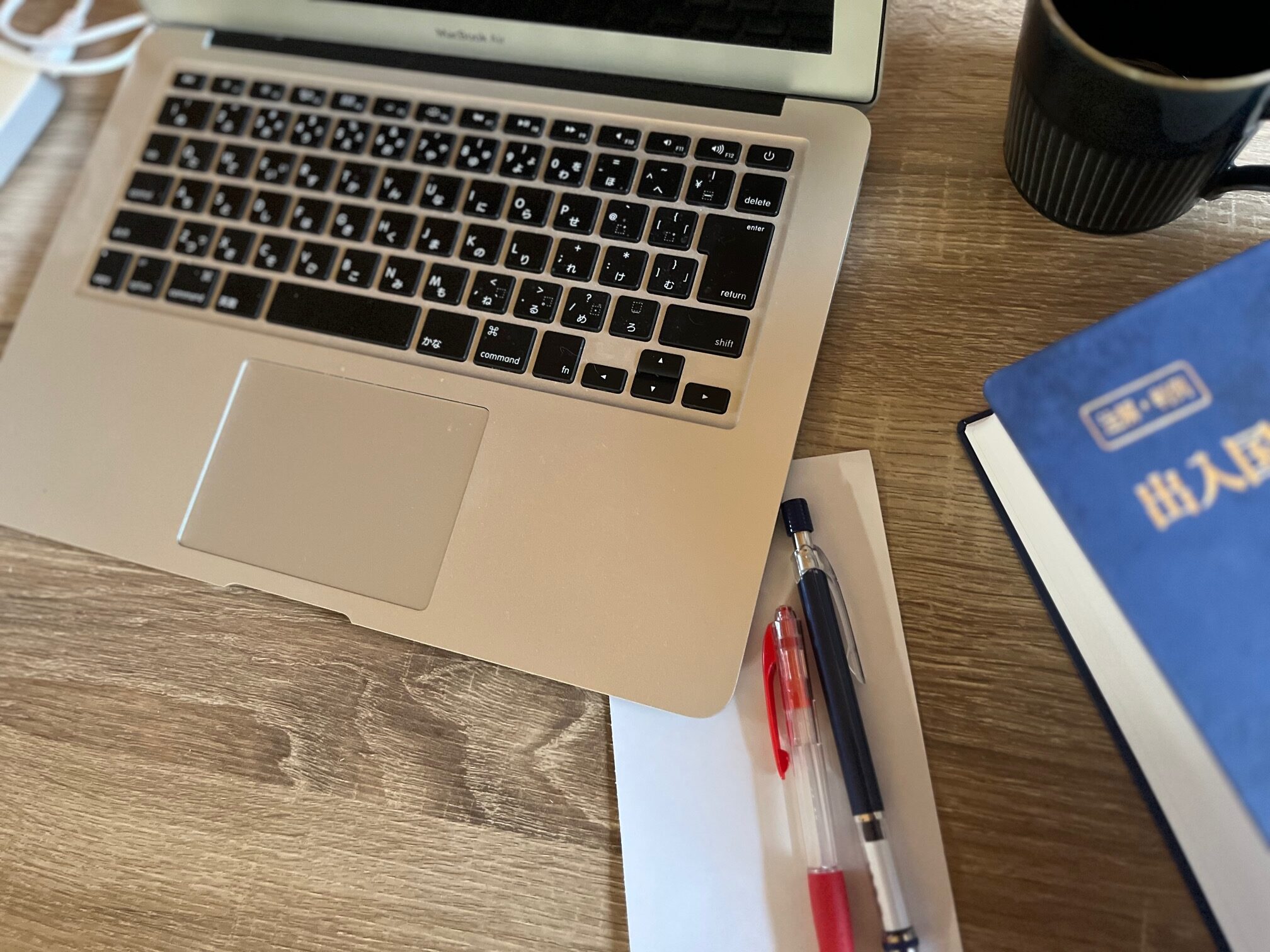本邦において行うことができる活動
まずは、技能実習制度について
技能実習法の認定を受けた技能実習計画に規定する、
イ 第1号企業単独型と第1号団体監理型(1年)
ロ 第2号企業単独型と第2号団体監理型(2年)
ハ 第3号企業単独型と第3号団体監理型(2年)
がある。
企業単独型とは海外に支店を持つ大企業などで、技能実習支援を単独ででき受け入れる。団体監理型は例えば商工会などの責任、監理の下で技能実習生を受け入れる。(アンスキルド)
各々規定に基づいて、講習を受け及び技能等(技能、技術、知識)に係る業務に従事することになる。
2号においては、2年目、3年目の技能実習生として1号において修得した技能等に習熟する活動を行います。3号においては、優良な監理団体及び実習実施者において2号を修了した後に一旦帰国して、一か月以上置いた後に再度入国して最長2年技能等を習熟する活動を行うことができる。
技能実習制度
技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年を一定期間受入れ、技能、技術を習得させ、彼らが帰国後に日本で習得した技術を活用することにより、母国の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度です。そしてそれらを運用するのが入管法に規定があるように技能実習法です。技能実習は外国人の出入国管理行政と技能等の習得という人材開発行政と密接に関わり、法務省と厚生労働省(実際は外国人技能実習機構OTIT)それぞれの知見を活かしていくことによる両省の共管としたものです。
必要な外国人材は?技能実習制度から育成就労制度へ
フルタイムで働ける人 ⇒ 最低限の日本語能力と業務知識を持っている人材が必要 ⇒ 受け入れ後に教育・研修を設けることが前提 ⇒ 技能実習生(2027年には育成終了制度に移行。以下の表参考)
育成就労制度は原則3年の在留期間で、未熟練の外国人労働者を即戦力と位置づけられる「特定技能1号」の技能水準に育てることを目的とする。熟練技能が必要な「特定技能2号」まで取得すれば、家族帯同の無期限就労が可能になる。
| 技能実習 |
| 技能実習生 |
| 技能実習実施者(受入れ企業) |
| 監理団体(監理組合) |
| 外国人技能実習機構 |
| 技能実習計画 |
| 育成就労 |
| 育成就労外国人 |
| 育成就労実施者 |
| 監理支援機関 |
| 外国人育成就労機構 |
| 育成就労計画 |
外国人技能実習制度についての詳細はこちらのPDFから
先に述べたように、技能実習制度は1号、2号、3号とあり、各々イ、ロと全部で6種類あります。イは企業監理型そしてロは団体監理型です。令和6年末時点で技能実習制度に占める団体監理型の割合は98.6%でした。
団体監理型が中心。(団体管理型98.4%、企業管理型1.6%-令和6年末)
団体監理型の技能実習生の受け入れにおいては、単独では技能実習生を受け入れることができない中小企業に国際貢献の道を開くため、一定の公的性格を有する監理団体(商工会など)が間に入り、技能実習制度が適正に行われることを目的としたものです。監理団体、実習実施者(受け入れ企業)には、それぞれに課された要件があります。そして監理団体、実習実施者各々において、技能実習計画に基づいて技能実習が適正に実施されているか、しているかについて、その実施状況を確認し、適切に管理することになります。
外部監査制度
また技能実習制度においては法人外部から監査する制度があります。外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適切に行われているかの監査を、監理団体から選任を受けた者が実施します。外部監査人は過去3年以内に養成講習を修了した者がその任に当たります。これには行政書士が大いに関わっています。
外部監査人の業務には、
①通常の外部監査で、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。その結果、外部監査報告書を作成して監理団体へ提出します。
監査業務として、
責任役員及び管理責任者から報告を受ける。
申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他物件を閲覧する。
②同行監査で、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認する。その結果、同行監査を書類として作成し、監理団体へ提出する。
外国人雇用について
企業が初めて外国人を雇用すると、ハローワークに外国人雇用状況の届出が義務付け。採用時と離職時の両方で届出が必要で、怠れば罰則があります。
社会保障協定については、自国と相手国との二国間協定である社会保障協定の制度があります。日本は現在20数か国と協定を結んでいます。また、年金の脱退一時金制度。一定の要件を満たせば、払い込んだ保険料の額に応じた一定の金額が請求できます。
特定技能制度
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性がでてきているため、生産性の向上や国内人材確保のための取組をおこなってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
特定技能制度には特定技能1号と特定技能2号がある。特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。特定技能制度は技能実習制度とは異なり就労を目的とします。家族帯同は不可。在留期間は法務大臣が指定する期間(1年を超えないい範囲)で、最長5年まで。現在特定産業分野は16分野に指定されています。(2024年5月現在)それぞれの分野ごとに従事する業務内容が決まっていて、従事する業務内容とのマッチングが大事です。特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留資格該当性
法務省令で定める
特定技能1号
相当程度の知識又は経験を必要とする
法務大臣が指定する本邦の公私の機関
雇用に関する契約
特定技能2号
熟練した技能
上陸許可基準
特定技能は技能実習制度との連続性が強いことから、技能実習制度において問題となった事例への対応が同様に採られている。例えば保証金の問題や違約金の問題など、日本における外国人の活動の自由を拘束するなどです。(被用者の自由意志)また、入管政策上の見地から、対象者を被退去強制者の引き取りを拒否しない国・地域の旅券所持者に限定している。(イラン、イスラム共和国以外の国・地域)
特定技能1号(セミスキルド)
技能実習2号から移行する外国人とそして国内国外で評価試験を受けて合格した外国人とがいる。いずれも日本語はN4(JLPT)相当以上の試験に合格が必要です。くどいようですが、職種名と作業名と業務区分のマッチングはとても大事です。
ところで、技能実習2号から特定技能1号への移行について注目点。技能実習を修了した後は、原則として母国に帰国する必要があります。技能実習から別のビザに変更するためには、原則として一度帰国して、技能実習で学んだことを母国へ移転する必要がある。それが技能実習制度の趣旨でであるからです。しかし、例外はあります。特定技能に限っては特例措置として、技能実習2号終了後、帰国することなく特定技能1号に移行することが認められています。特定技能1号は在留できる期限が5年間に限定されているので、5年後に母国に帰国して技術移転すればいいという考えからです。
さて、先に述べた特定技能1号の16の特定産業分野には、各々の受入れ見込み数(5年間)が決まっています。
介護 135,000
ビルクリーニング 37,000
工業製品製造業 173,000
建設 80,000
造船・舶用工業 36,000
自動車整備 10,000
航空 4,400
宿泊 23,000
自動車運送業 24,5000
鉄道 3,800
農業 78,000
漁協 17,000
飲食料業製造業 139,000
外食業 53,000
林業 1,000
木工産業 5,000
合計82万人余。これ以外の業種で特定技能外国人を雇うことはできません。
(近年、人手不足が特に深刻な分野に対応するため、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加さました。合計16分野は上記の通り。そして「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」といった分野の追加も検討されておます。適用範囲は今後も広がっていく見込みのようです。)
特定技能外国人に関する基準
受け入れ機関に関する基準
支援計画に関する基準
特定技能における分野別の協議会
特定技能における二国間協議(MOC)
保証金を徴収するなど悪質な仲介業者(ブローカー)等の介在防止のため、二国間取決めなどの政府間文書の作成等、必要な方策を講じる。(政府基本方針 令和7年3月)
次に、特定技能2号(スキルド)
- 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
- 在留期間は3年、1年または6か月ごとの更新で、上限なし
- 技能水準は試験などで確認
- 日本語能力は試験での確認は不要
- 家族の帯同は、配偶者子供については要件を満たせば可能
- 受入れ機関、登録支援機関による支援は不要
- 永住権の取得が可能
上記が特定技能2号の基本的なことだが、1号と比較するとかなり違いがある。1号では、在留期間は通算で5年だし、支援機関の支援も対象。また家族の帯同は認められていない。
特定技能2号の業務内容は11分野。1号で言うところの介護、自動車運送、鉄道、林業、木工産業は2号にはない。尚、11分野中で注意したいのは建設業です。
特定技能「建設業」について
- 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入
- 建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業登録
- 国土交通大臣による建設特定技能受け入れ計画の認定
- 加入・登録・申請をしなければ「特定技能」の申請ができない
- 建設分野特定技能2号試験合格又は技能検定1級合格と班長としての実務経験。国交省の定める期間の実務経験が必要
以下10分野
ビルクリーニング 複数の作業員を指導しながら業務に従事し、現場を監理するものとして実務経験2年以上。
工業製品製造 特定技能2号評価試験合格。ビジネス・キャリアを検定3級合格。日本国内に拠点を持つ企業の製造現場で3年以上の実務経験。
JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)について(2025/6/26)
工業製品製造業分野の特定技能外国人の受入れに関する事業を実施する法人。
特定技能制度の工業製品製造業分野において、特定技能外国人を受け入れる場合は、今後、全ての受入れ事業所がこの法人に加入することになります。(JITCOのHPより)
賛助会員の入会手続きはこちら
造船・舶用工業 造船・舶用工業で複数の作業員を指導・命令・管理する監督者としての2年以上の実務経験。
自動車整備 特定技能2号評価試験合格。認証を受けた現場で3年以上の実務経験。自動車整備士技能検定2級は実務経験不問。
航空 空港グランドハンドリング業務で特定技能2号評価試験合格。航空機整備業務で特定技能2号評価試験に合格。整備現場度3年以上の経験要。
宿泊 特定技能2号評価試験に合格。複数の従業員を指導し、フロント、企画、広報、接客、レストランサービスなどに管理。2年以上の実務経験。
農業 2号農業技能測定試験に合格。指導・管理。
漁業 特定技能2号評価試験・日本語能力試験N3以上。養殖業は2号漁業技能測定試験・日本語能力試験N3以上。指導・管理。
飲食料品製造 特定技能2号評価試験合格。指導・管理。実務経験2年以上。
外食産業 外食業特定技能2号技能測定試験の合格。指導・管理2年以上の実務経験。日本号能力試験N3以上合格。
特定技能1号の取得手続きは複雑で、多くの書類が必要となります。
基本的な流れとしては、2通り。
技能実習からの移行組と試験突破組(国内・国外)
| 技能実習からの移行組 | 試験突破組(国内・国外) |
| 試験合格又は技能実習2号修了 | 人材の選定と試験合格の確認 |
| 雇用契約の締結 | 雇用契約の締結 |
| 支援計画策定(事前ガイダンス) | 支援計画の策定 |
| 出入国在留管理局への申請 | 事前ガイダンスと健康診断 |
| 就労開始・生活オリエンテーション | 出入国在留管理局への申請 |
| COE交付とビザ申請 | |
| 入国と就労開始・生活オリエンテーション |